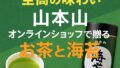ごきげんよう。
「ケンタロウのデリバリーキッチン」へようこそ。
※デリバリーキッチンについて知りたい方はコチラより♪
●政治が変わる今、家庭の「食」を守るには?
2025年夏、日本はひとつの政治の転換期を迎えています。
この変化が、私たちの日常生活にどのような影響を与えるのか…特に「食の安全」という視点で見ると、今こそ考えるべきタイミングです。
実は私自身、生後10ヵ月を迎える息子を持つ40代の共働きサラリーマンパパです。
日々の仕事と育児の両立に追われながら、気がつけば
「今日のごはん、ちゃんと安全なものを選べているだろうか…?」
と不安になることが増えました。
●安全な食材は「当たり前」ではなくなる?
農林水産省が公表した最新統計(2024年版)によると、日本の食料自給率はわずか37%(カロリーベース)。
つまり、私たちが口にする食材のほとんどが海外からの輸入に頼っています。
これに加えて、政治の動きによって農業支援制度の見直しや食品安全基準の規制緩和が進めば、今後「何が安全で、何がそうでないか」の見極めが一層難しくなる可能性もあるのです。
●乳幼児期こそ“見えないリスク”に敏感でいたい
生後10ヵ月になる我が子は、離乳食も進み、1歳を前にいろいろな味に興味を持つようになりました。
ですが、野菜は相変わらず苦手…。
とくににんじんとピーマンなどは、スプーンを近づけただけで顔をそむけてしまいます。
そんな中、我が家が活用し始めたのが、原材料・産地・添加物などが明確に表示された宅配食サービスです。
たとえば「国産野菜のみ使用」「農薬・化学調味料不使用」「アレルゲン対応済み」といった点が公式サイトにしっかり記載されていると、育児中の親としては本当に安心感が違います。
●「安全の基準」は自分で選ぶ時代へ
以前は「スーパーに並んでいる=安全」と思っていた私も、最近ではすっかり意識が変わりました。
例えば、同じ冷凍ハンバーグでも、どこで作られたのか、どんな素材を使っているのか、どんな管理体制で製造されているのか…。それらが見えない商品には手を伸ばしづらくなったのです。
この変化は私だけではありません。
日経電子版の特集『食と家計』でも、「家計における“安心代”としての宅配食品ニーズが高まっている」との報告があります。
●忙しいパパ・ママにとっての「宅配食」の魅力とは
宅配食は、ただ“楽”なだけではありません。
- 調理の時短:電子レンジや湯せんだけで食べられる
- 安全性の可視化:原材料・産地・製造元が明記されている
- 子どもも食べやすい味付け:乳幼児向け専用メニューも豊富
特に共働き世帯にとっては、「考えなくていい」=精神的な余裕をもたらす大きなメリットでもあります。
●息子が“にんじん”を食べてくれた日
これまでどんなに工夫しても避けていたにんじん。
すりつぶしても、スープに混ぜても、ほんの少し口に入れるだけでイヤイヤ……。
それが、ある宅配の離乳食セットに入っていた「人参と白身魚のやわらか煮ペースト」を初めて食べさせた日──。
息子はスプーンでひと口、ぺろりと食べて、モグモグ……そして、にっこり。
その瞬間、「あぁ、これでよかったんだ」と心の底から思えました。
宅配離乳食を通して得られたのは、単なる“栄養”や“便利さ”ではありません。
「この子に安心して食べさせられるものを選べている」という確かな実感だったのです。
●今後の“食の選択”において重要になる3つの視点
政治が変わり、社会が揺れ動く今だからこそ、私たちは日々の「食」をどう選ぶべきか。
そのヒントとして、以下の3つを意識することをおすすめします。
- 信頼できる情報源に基づく判断
- 価格だけでなく“見えない価値”に目を向ける
- 忙しい毎日でも無理なく続けられる方法を選ぶ
●さいごに:変わる時代だからこそ、食の“軸”を持とう
政治や経済がどう変化しようとも、「子どもには安全なものを食べさせたい」という親の想いは変わりません。
そのために私が選んだのが、明確な基準とトレーサビリティがある宅配食品です。
これからも、家族の安心を守る「食の選択肢」として、宅配サービスの可能性をブログで発信していきたいと思います。
【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】
最新情報はXで発信中!
リアルな声等を @busylifekitchen で毎日つぶやいています!