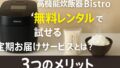ごきげんよう。
「ケンタロウのデリバリーキッチン」へようこそ。
※デリバリーキッチンについて知りたい方はコチラより♪
先日、X(旧Twitter)のDMで非常に考えさせられるご質問をいただきました。
内容を要約するとこうです。
「選挙で『消費税撤廃』を掲げる政党が出てきて話題になっているけれど、
もし本当に消費税が0%になったら、私たち一般家庭の生活はどのくらい楽になるのでしょうか?
メディアで語られる“平均的な家庭像”が本当に自分たちに当てはまるのか、ちょっと疑問で…」
このDMを読んだとき、「これは、まさに家庭の台所を預かる一人として避けて通れない話題だ」と感じました。
というのも、我が家も0歳の息子を育てる共働き家庭。
オムツ、ミルク、宅配弁当、食材、生活用品——どれもこれも消費税がかかるのが当たり前の日常です。
…と云っても当ブログは「宅配食品サービス」をメインにした、子育てパパ目線のブログ。
政治は詳しくありませんが、ケンタロウなりに調べた事をここに書いていこうと思います。
たとえば、税込価格でしか買い物していないと、「どれくらい税金を払っているのか」を意識する機会は意外と少ないもの。
でも、仮に10%の消費税が0%になったら?
「年間で数万円単位の“隠れた出費”がまるごと浮く」かもしれません。
このブログは宅配食品サービスを中心に発信していますが、実はこの分野でも消費税の影響はかなり大きいのです。
たとえば、1食あたり700円のミールキットを週5日×4週間使った場合、月額では14,000円(税抜)→15,400円(税込)。
つまり、毎月1,400円が“消費税”という形で消えているのです。
これはあくまで一例にすぎませんが、「消費税が撤廃されたら、どれだけ家計が楽になるのか?」という問いには、確かにリアルな価値があります。
そこで本記事では、以下の視点からわかりやすく解説していきます。
- 平均的な家庭が1年間に払っている消費税額の目安
- 共働き・子育て家庭における具体的な影響
- 宅配食品サービス利用者にとっての「お得になる金額」のシミュレーション
- 今すぐ取り入れられる“プチ節税的”な生活の工夫
「政治の話は難しい」と思う方でも、家計への影響を具体的に知ることで、ニュースの見方が変わるかもしれません。
ぜひ、最後までご覧ください。
消費税ゼロなら年間○万円浮く!まずは結論から
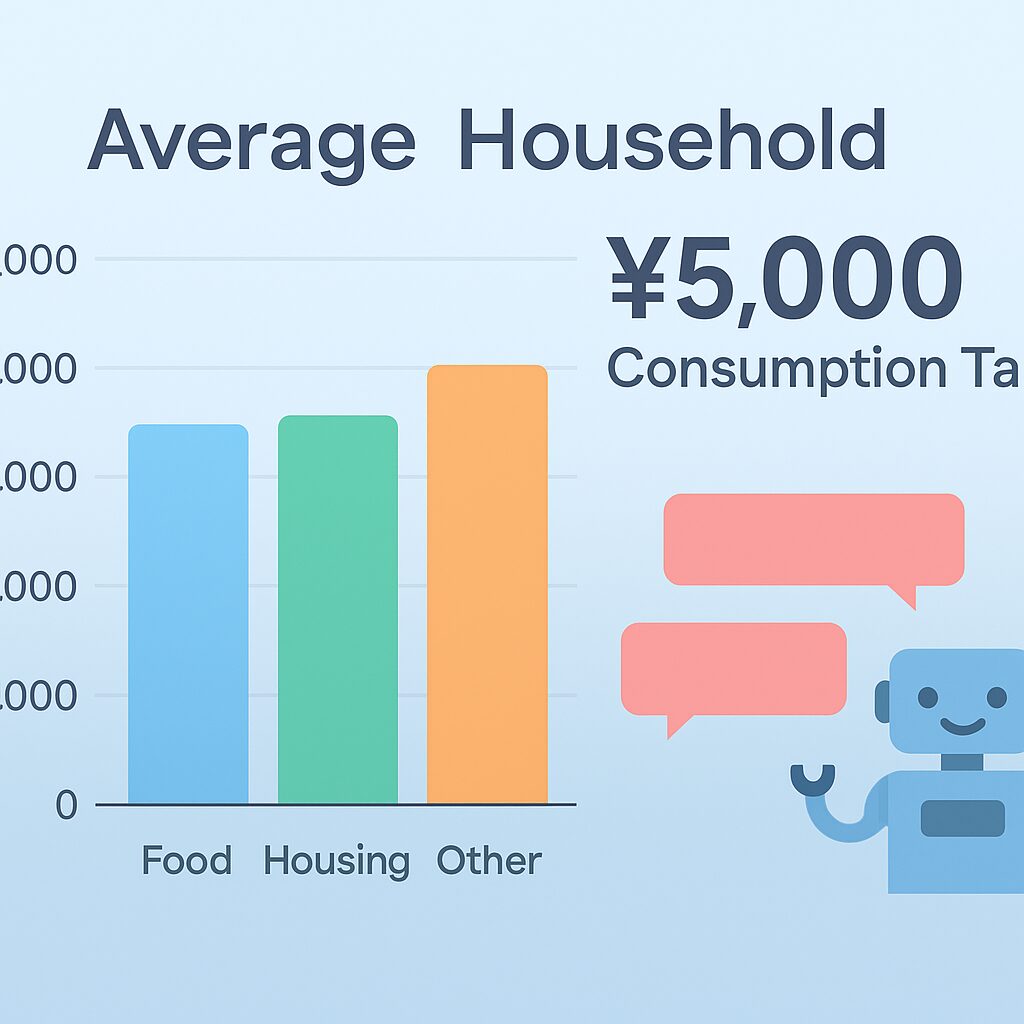
消費税が10%→0%に下がった場合年間で約8万~12万円のお得が見込めます。
なぜそんなに差が出るのか?
それには二つの重要な理由があります。
ひとつは生活必需品への支出が膨大だから、もうひとつは宅配食品やミールキットの利用頻度が高いからです。
① 食費・日用品
総務省の家計調査によれば、30~40代の共働き子育て家庭の年間生活支出は約400万円。
そのうち食料費と生活雑貨費で約120万円かかっています。
これに10%の消費税が適用されると、12万円の税金負担。
消費税ゼロになれば、文字通りそのまま浮く計算です。
② 宅配食品・ミールキット
当ブログで紹介している宅配ミールキットを例に取ると、1食あたり税抜700円が週20食で月々約14,000円、年間で168,000円。
消費税分は年間で約16,800円。思いのほか大きいですよね。(あくまで単純計算なので、もう少し浮きます)
③ 日用品・育児用品
オムツやミルク、おしりふきなど、育児用品にかかるコストは年間で約30~40万円。
その10%負担分は3万~4万円。0%になれば、その分が家計にゆとりになって返ってきます。
総合試算:モデル世帯の「隠れたお得額」
上記を合計すると、共働き&小さな子どもがいる家庭では…
毎年約8万~12万円がまるごと「消費税ゼロで賄われる」ことに。
もちろん、支出の多寡や買い物傾向により誤差はありますが、“誰でも実感できる金額”であることは間違いありません。
単純計算で考えると2万円貰うより、消費税撤廃の方が良さそうに感じる方もいるかもしれません。
消費税は“地味に”効いてくる。家庭の財布を圧迫する3つの現実

10%という数字だけを見ると、たかが数十円の違いに感じるかもしれません。
しかし、毎日使う生活必需品や食費、子育て用品にこの税率がかかり続けるとなれば、その影響は想像以上に大きくなります。
まず押さえておきたいのが、2019年に導入された「軽減税率」です。
食料品や新聞は8%、それ以外は10%という仕組みは、一見すると家計への配慮のようにも見えます。
ですが、実際の買い物の現場では“わかりにくさ”が先に立つのが実情です。
例えば、スーパーでパンは8%、店内のイートインスペースで食べると10%。
ミールキットは8%だが、栄養補助食品は10%。
この複雑さは、価格比較や家計管理を難しくする要因になっています。
さらに注目すべきは、税率が2%上がっただけでも、家計全体では数万円単位の負担増になるという点です。
実際、総務省の「家計調査(2023年)」によれば、食費・日用品・教育費などの非課税対象以外の支出は年間でおよそ350万円前後。
そこに10%の税がかかると、35万円前後が“消費税”として支払われていることになります。
もしこれが8%だった場合は約28万円。
その差は7万円。
そして、これはあくまで税率2%の違いによるもの。
たった2%でも、子どもの学費1ヶ月分、家族での外食2~3回分に相当する額です。
「でも、うちはそんなに使っていないから関係ない」と感じる方もいるかもしれません。
しかし実際は、消費税は所得に関係なく一律でかかるため、低所得世帯ほど“税の重み”を強く感じるという特徴があります。
たとえば、年収400万円の家庭と800万円の家庭が、それぞれ同じ5万円分の食料品を購入した場合、支払う消費税はどちらも5,000円。
つまり、可処分所得に占める割合は年収が低いほど高くなるのです。
このように、消費税は金額的にも心理的にも“見えにくいけれど確実に効いてくる家計負担”を生み出しています。
特に子どものいる家庭では、オムツやミルクなど“頻繁に購入するもの”に毎回課税されるため、「小さな出費の積み重ね」が思った以上に家計を圧迫します。
日々の暮らしでは実感しにくいかもしれませんが、1ヶ月、1年と時間が経つごとにその差は確実に広がっていきます。
そして、その差はちょっとした家族旅行や新しい家電の買い替えなど、“心の余裕”にも影響を与えるようになります。
消費税ゼロを待たずとも“節税的”に家計が助かる宅配食品の使い方とは?
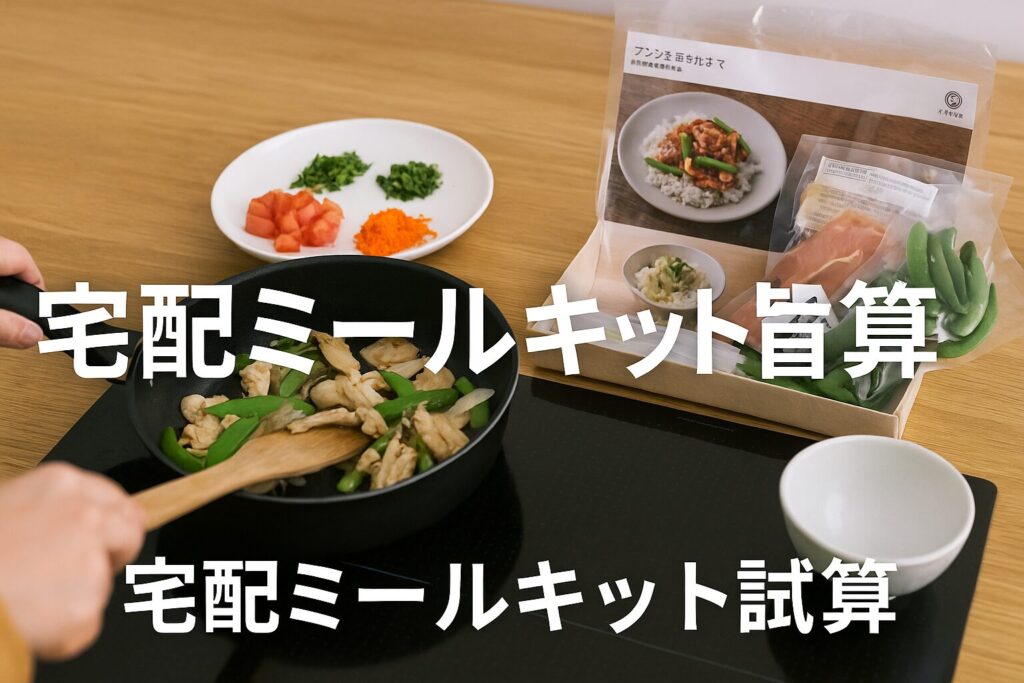
「消費税がゼロになるかどうかは分からない。でも、日々の出費を少しでも抑えたい」
——そう感じている方は多いのではないでしょうか。
実は、消費税の有無に関わらず、“節税的に”使える宅配食品サービスの選び方と使い方があります。
まず注目すべきは、定期購入やサブスク型サービスです。
一見すると「毎週届く=出費が増える」と思われがちですが、実はその逆。
定期購入には割引が付くケースが多く、都度購入より平均5〜10%安く抑えられる仕組みになっています。
これは言い換えれば、“実質的な消費税還元”のような効果があります。
また、私自身も導入しているのが「まとめ買い+冷凍保存」での活用。
冷凍タイプのミールキットやおかずセットを1回で5〜10食分まとめて注文することで、配送料が無料になったり、キャンペーン割引が適用されるケースも少なくありません。
1食あたりの実質価格を大幅に下げることができるのです。
さらに特筆すべきは、宅配食品が「無駄買いを防げる」という点。
スーパーでの“ついで買い”やコンビニでの衝動買いは、家計簿に記録しづらく、いつの間にか出費が増える元凶です。
宅配型なら、あらかじめ予算を決めて注文するため、月間の食費をコントロールしやすいという強みがあります。
特に、食費管理が難しい共働き・子育て家庭には、この“自動化された支出コントロール”が大きな助けになります。
料理の頻度・内容・人数に応じた最適なプランを組めば、外食や中食(惣菜)の頻度も自然と下がり、全体としての支出は確実に安定していきます。
そして、最後に「本当に必要なものにだけお金を使える」という意識改革も忘れてはいけません。
宅配サービスを通じて得られるのは、時短や利便性だけではありません。“計画的な消費”という習慣が身に付き、結果として家計全体が“節税的”に生まれ変わっていくのです。
もちろん、無理に高額な宅配サービスを選ぶ必要はありません。
大切なのは、自分たちのライフスタイルに合ったサービスを見つけ、賢く使いこなすことです。
今ある選択肢の中でできることを、できるところから始めてみる。
それが、消費税に振り回されない家庭づくりの第一歩になるのではないでしょうか。
政治と家庭は無関係ではない。だからこそ、数字に目を向けよう

消費税の議論を見て、「どうせ自分には関係ない」と感じる方は少なくありません。
選挙、政策、国会といった言葉はどこか遠くの出来事に思えがちです。
しかし、今回改めて家計目線で試算してみて分かったのは、“政治の決定は、私たちの日常生活にダイレクトに影響している”という事実です。
消費税が0%になったら、育児家庭であれば年間8万〜12万円の節約が可能だという試算。
それは、ただの数字の話ではなく、家族で過ごす時間や経験の選択肢が増えるという、生活の質に直結するテーマです。
例えば、子どもの初めての誕生日にレストランで食事ができるか、旅行ができるか、あるいはその資金を積立に回せるか。
すべては、“家計のゆとり”にかかっています。
だからこそ、政治的な議題にも家庭目線で関心を持つことが求められる時代です。
ただし、それは難しいことではありません。
まずは「月々、どれだけ消費税を払っているのか?」に意識を向けるだけでも、自分ごととして捉えられるようになります。
たとえば、普段の買い物レシートを見返すだけでも、消費税がどれほど積み上がっているかが見えてきます。
1日100円、月で3,000円、年で36,000円。
少し意識を変えるだけで、今まで見えなかった“家計の漏れ”が可視化されるようになるのです。
そして、その視点を持った上で宅配食品サービスを選ぶと、判断軸が大きく変わります。
時短だけでなく、「年間トータルでいくら節約できるか?」という視点を持てるようになり、“単価の安さ”だけでなく“コスパの高さ”で選べるようになるのです。
また、育児家庭の場合は、自分の買い物行動が子どもの未来にも影響することを忘れてはいけません。
子どもが口にする食品の質、教育費に回せる余裕、安全な住環境の整備——どれも“今日の選択”の積み重ねです。
そう考えると、消費税や物価、サービスの選び方など、すべてが“家庭経済の政治”と密接に関係していると実感します。
政治を難しく捉える必要はありません。
選挙のたびに候補者の政策をチェックする、税の仕組みを少しだけ調べてみる。
それだけでも、「家計を守るための意識」が養われていくはずです。
当ブログでは今後も、家族にとって本当に必要なサービスや情報を数字と実例を交えて発信していきます。
家庭に役立つ視点を持ち、自分たちの未来を自分たちで守っていくこと。
それこそが、この時代を乗り切るための小さな武器だと信じています。
最後にここまで読んでくれたアナタは消費税の行方(節約)に大変関心がある方だと思います。
筆者は政治の事をとやかく云うつもりは毛頭ありませんが、自分の生活に直結する問題なので、自分が良いと思える政党へ1票を投じる事が、節約に繋がる可能性があります。
節約の為にも、7月20日(日)は選挙へ行きましょう!
選挙に行かなければ、今後4年間は消費税も変わらず、選挙に行けなかった自分を責める事になるでしょう。
それよりも、アナタが信じる政党へ清き1票を投じて、節約になるかもしれない「未来」を選んでみてはいかがでしょうか?
最新情報はXで発信中!
リアルな声等を @busylifekitchen で毎日つぶやいています!